商品タイプで絞り込む
-
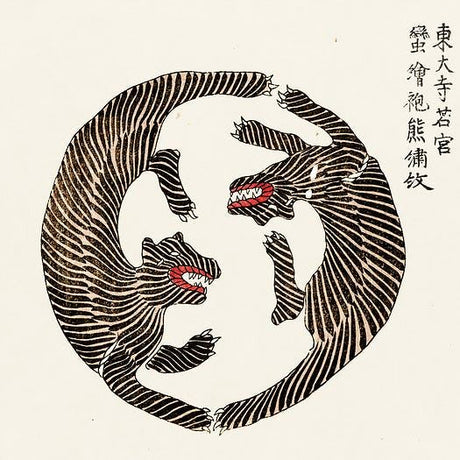
Yatsuo no Tsubaki(八丘椿)
- ベストセラー
Yatsuo no Tsubaki(八丘椿)
Crane from Yatsuo no tsubaki by Taguchi Tomoki - 八丘椿 Memo.
セール価格 ¥2,800 定価 ¥3,480単価 /利用不可

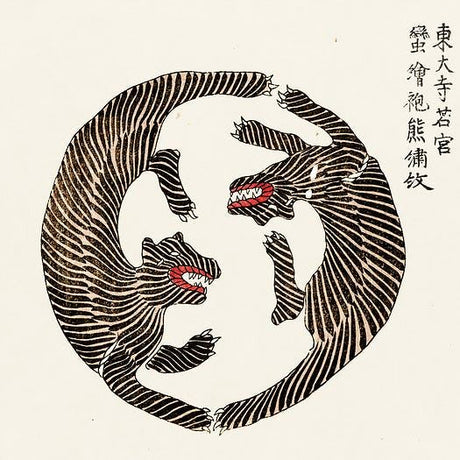
Yatsuo no Tsubaki(八丘椿)
Yatsuo no Tsubaki(八丘椿)
Crane from Yatsuo no tsubaki by Taguchi Tomoki - 八丘椿 Memo.