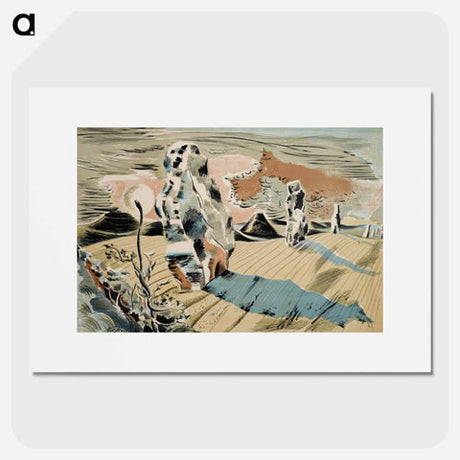artlog.
-

-

【作品解説もあり!】レンブラント・ファン・レイン の作品をアートパネルで。名作アートを身近に!
tettestaff |
-
-

ルーアン大聖堂の魅力を解説!モネはなぜ連作を制作したのか
PRINTSTAFF |
-
-

-

-
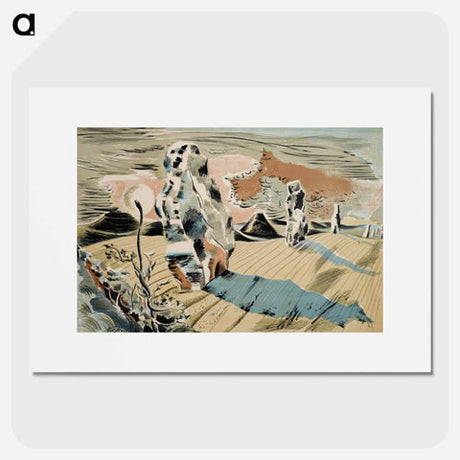
-

-




tettestaff |

PRINTSTAFF |