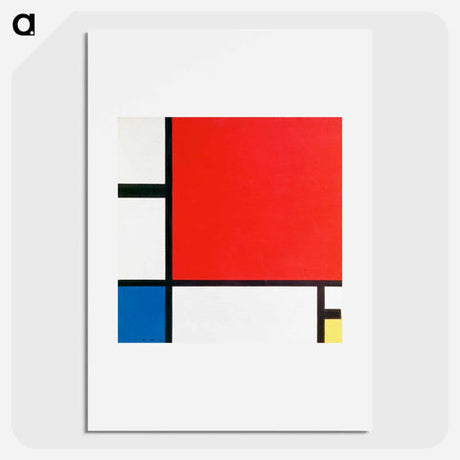artlog.
-
-

-

ポワンティリスムとは?スーラが用いた点描技法の意味と特徴を解説
PRINTSTAFF |
-

-

-
【作品解説もあり!】ポール ナッシュ の作品をアートパネルで。名作アートを身近に!
tettestaff |
-
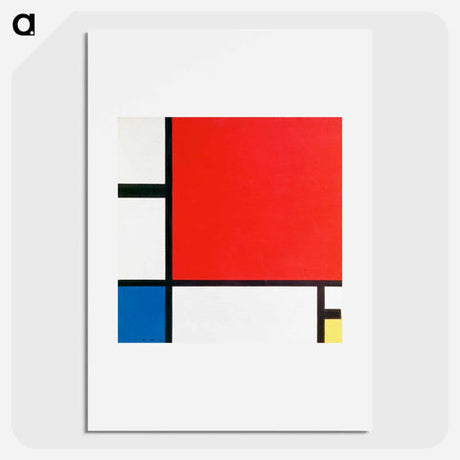
-

-
-

ゴッホのポスターで魅せる!お部屋がおしゃれになるインテリア&飾り方
PRINTSTAFF |